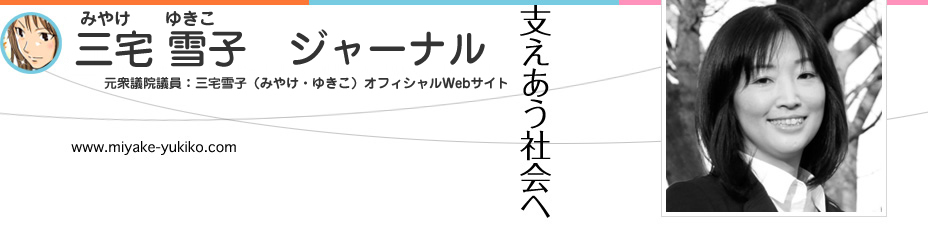私の尊敬する方に、知的障がい者の雇用率が70%を超えていることで有名な日本理化学工業の大山泰弘会長がいらっしゃいます。
80歳は超えているかどうかですが、講演で全国を飛び回っていらっしゃいます。
話し方こそ穏やかですが、行動力は超人的。エネルギッシュな方です。(現在は療養中)
大山会長については、拙著『福祉と私』の中でも取り上げさせて頂きました。
幸運なことにこの会社に勤めることができた人がいます。
毎日、決まった時間に決して遅刻することなく、元気に出勤しています。
大山会長はこうおっしゃいます。
「人間の究極の幸せは、愛されること、ほめられること、役に立つこと、必要とされること」
これらを満たしているから、皆が幸せそうに毎日会社に通っているのでしょう。
仕事がなくなるということは、その人にとって単に収入が途絶えること以上に大きなダメ―ジを与える可能性があるのではないでしょうか?
それは「必要とされること」に関わってくるからです。
雇用が今、心配されています。私も本当に心配しています。
総理は「雇用が増えた」と胸を張っていますが、しかし、実態は、非正規雇用者が106万人増え、正社員が53万人減ったというだけ。
企業の人件費カットの結果です。これが政府の言う「人材の流動化」なんでしょうか?
大企業のトップが集められた「産業競争力会議」では、解雇規制の緩和、限定正社員など企業の側にとって都合のいい雇用の形が話し合われているように見えます。
大企業のトップが有識者会議のメンバーなのがいけないというわけではありません。
ここに、日本の9割以上を占める中小零細企業の代表者や労働者側の代表がいないことは、やはり、おのずと偏った結論が導き出されてしまう懸念があ
ります。
大山会長がよくおっしゃるもうひとつ重要な言葉があります。
「仕事に人を合わせるのではなく、人に仕事を合わせる」
日本理化学工業に行くと、知的障がいがある人たちが仕事をしやすいように様々な工夫がされています。
はかりひとつにしても、数字ではなく、重しに色をつけて区別できるように工夫している、など。
こうした考え方は、一般企業にも当てはめることはできないでしょうか?
会社の中には様々な仕事があります。たまたま自分が苦手とする業務を担当し、思うように仕事ができず 評価が低くなってしまうケースもあるかもしれません。
しかし、その人にあった業務を担当させたら、周囲もあっと驚くような成績をあげることもあるかもしれません。そう考えるとまず、企業の中で「人材の流動化」をすればいいのでないかと考えます。
「人は企業の財産」この言葉は死語になってしまったのでしょうか?安定した雇用のもとでこそ、消費が活発化し、景気に寄与する、ごく普通に考えれば、それが経済成長に繋がるはず。
1に雇用、2に雇用、3に雇用と一時期しきりに言われていました。なぜか、この言葉はすぐにTPPや消費税増税にかき消されてしまいましたが・・・これだけはよかった(失礼!)
雇用の大切さ、このことをもう一度政府与党には考えてもらいたいと心から思
います。
(加筆しています)